光と色 [科学系]
「赤い本」を普通に見ているとする。
自然な(素朴実在論的な)見方では、本という実在物があり、その表面には色が付着していて、その色は「赤」である、と見なしている。
しかし、「赤い本」はいつも赤いわけではない。
真っ暗だと、当然「黒い」だけである。そして「光」の加減に応じて本の色の濃淡は変化する。しかも「光の色」によっても対象の色は変化する。
つまり、「対象物の色」というのは対象に付着する色ではなく、「対象の表面」と「光の反射」との「相関」関係にあることがわかる。光がないと、色もないわけである。
科学的な説明を加えてみると、「赤い本」の場合、光の反射により「赤」と見えるのであるが、実際には、当たっている光は全て反射しているのではなく、青緑色の光を吸収し、残りの赤い光を反射している。その反射した「赤い光」によって「赤い本」は「赤」に見える。つまり人は、吸収されない「残りの光」を見ている。
光は目で捉えるのであるが、目の網膜には光の色を識別する細胞(錐体)があり、赤、青、黄という三種類の錐体で光を感知し、その情報から視神経を経て脳の視覚系部分により色を判断している。
この科学的説明は、現象学の「射映」原理の補完にもなっている。
「射映」とは、「意識に対し与えられるものから、一面的に映し出す」ということであり、事物を「現れ」として映し出す意識の能力を表している。
色についても、色彩の射映原理に従っており、意識に与えられる何らかの色彩的素材から色を映し出す人間の色彩映写能力として考えられる。
色盲(色覚異常)では、色の射映能力に多くの人と違いがあるのであり、赤と緑の区別がつきにくい場合には、色彩射映構造がその部分で人と違っているということである。
人は「対象物の色」を見ていると思っているが、「色を色として映し出す」のは人間の自我の能力である。
「対象物」は自我と相関的なものであり、「対象の色」もまたそうである。
テレビは「光をどう発光するか」であり、写真は「光をどう反射するか」である。色の調整は人間の現実的感覚の満足度での調整であり、それが技術である。
テレビや写真は、「実物に近いもの」を作るのではなく、「実物に近いように見えるもの」を作るのであり、実物に近いように錯覚させる技術である。
時間の謎(2) [科学系]
哲学にも「時間」の議論は様々あるが、物理学においても「時間」の定義は明確に決まっているわけではない。その定義は理論に応じて変動する。
(本文では「時間」は「客観的時間」を指している)
ニュートン、ライプニッツ、マッハ、アインシュタインなど「時間」だけでなく「空間」においてもその定義は様々である。
そもそも「時間や空間を定義する」とはどういうことなのか?
「実体とは何か」という哲学問題は保留するとしても、「時間」は実体的なものではない。誰も「時計」を見たことはあるが、「時間」の実体を見たことはない。時計は単に一定に動いているだけである。
等速直線運動する物体が目盛上を動いているとする。これを「時計」と考えることも可能であり、物体が円運動すれば、時計と同じような原理である。従って、「時計」は「運動が等速である」ことを満たせば、後は目盛りの打ち方だけとなる。
つまり「(時計の)時間」とは、自転や原子運動など等速運動する(と人間が判断した)基準存在との「単位運動の比較等比」である。すなわち「基準運動との比例」である。
また「空間」も同様であり、実際に「空間の実体」は何かとは言い難い。目の前に空間があるのは確かであるが、空間を「定義」するのはなかなか難しい。幾何学的な三次元空間を通常はイメージするが、日常の事実的空間と幾何学的な空間を「等しい」とすることはできない。
日常の空間はあくまで感性的に経験され構成される生活空間である。幾何的な三次元空間は理念的な空間である。
生活空間を理念的三次元的に表現するとどうなるのか?幾何空間も基準を必要とするが、基準を設けるには何を基準にすればいいのか?「観測者の目」なのか「観測者の意識」なのか「地球のある地点」なのか「宇宙のある地点」なのか?xyz軸はどうとるのか?その軸は、地球の表面(球面)に対してどのような関係にあるのか?複数の観測者がいる場合、その観測点間の関係はどうなるのか?
「時間や空間は、我々が考えるための手だてであって、生きている環境ではない」(アインシュタイン)
物理学は事実(現実)を対象とする。その場合、「事実」をどう「理念化」するのかという定義問題が必ず発生する。
相対性理論では「空間は曲がる」。実際は太陽など重力の大きい物体の側を「光」などが通過すると「光の軌跡」が曲がるのだが、それを「空間が曲がる」と解釈している。(物体により時空は影響を受け、「時空」が曲がる)
このことを「空間が曲がる」とするのか、それとも「空間は同じ(ニュートン的絶対空間)だが、単に光(等)の進行が重力(物体)により曲がる」とするのかは空間の定義(理論)次第である。どちらも同じ事象を指しているのであり、「空間」の解釈が違うだけである。相対性理論の扱う事象では、空間を曲げないと(空間概念の意味がなくなり)理論化は難しいのかも知れない。
だから「正しい空間の定義」が存在する訳ではないと考えた方がいい。
では定義とは何なのか?
「時間の定義は力学の方程式ができる限り簡単になるような定義でなければならない」(ポアンカレ)
つまり、事実学(物理学)としての時間や空間の定義は、「正しい定義」ではなく方程式が簡単になる「最適な定義」ということである。しかし、「最適な定義」を巡り議論になるのには違いない。それは進歩した理論に準じた「最適な定義」であることはやむを得ないのかも知れない。
哲学の議論と物理学の議論を同列で語るのは相当に困難である。事実事象の「理論化」としてある物理は「ある制限付き」の理論(ある条件下で近似的に成り立つ理論)であることが原理上避けられない。従って、いかなる理論も「厳密に正しい理論(基礎づけられた理論)」とは言いにくく、また、実用的な条件下で必要十分な精度の理論であれば「間違った理論」とも言いにくい。人間にとって満足する精度での実験結果と理論との一致なので、数学のように「正誤」ではなく、ある程度「幅のある判断」となる。
ニュートン力学で「十分通用する現実条件内」での理論は、その後に新しい理論が出現しても、それが間違いになるとは言えない。
理念的な「厳密理論」ではなく「実用理論」として考えるなら物理理論はある程度柔軟に利用されるものであり、それで十分な成果がある。しかしここに「定義」(等)を巡る異論が立ち現れることが宿命的となり、昔から論争がつきない(ようである)。
時間の謎(1) [科学系]
時間の超越論的(現象学的)理解については様々な疑問があるかもしれない。
(a) 客観的時間を表示する「時計」が、意識と分離できないとすると、寝ている時には「時計は動いていない」のか?
(b) 「過去とは過去意識」であり「未来とは未来意識」であり、「意識上の今しかない」ならば、過去の事実というのは一体何なのか?ビデオ録画されている「過去」は「過去」ではないのか?「未来」はいいとしても「過去」とは「幻想」なのか?
(c) 宇宙の過去を論じるのは不毛なのか?
これらを理解するには、自然な時間観から離れる必要がある。
(a) は、「寝ている時に時計は動いていないのか?」という疑問であるが、「寝ている時」には「時計が動くも、止まるも、その意識自体がない」ということで、「動いていないのではない」。
これは、「地球」でも同じであり、「目覚めて」地球の今や過去について思いを馳せられるのであり、「寝ている時」には「地球はない」のではなく、「対象を把握する自我意識がない」。
「主観」-「客観」という図式を頭から取り払わないといけない。
(a) は、主客図式を前提とした疑問である。「寝ている時」に「時計や電車は動いている」というのも、別の目覚めている人の認識であり、「目覚めている時でも」我々は全ての動きを完全に把握しているのではなく、意識の焦点に運動があるときに、その運動を把握する。「動く」も「動かない」も意識の注視による把握である。
目の前の空気の動きも微生物の動きもコンピュータの内部動作も実際は知らないのであり、それらをそもそも「知る」とは何かが問題であり、「対象」は意識相関的に把握されるものである。それらは、装置などを使って、ある観点で注視したときに動作(あるいは非動作)が把握される。
目の前のテレビは「動かない」が、地球が動いていることから言えば、地球外の目線では「動いている」。対象は「今、ここ」における相対的なものである。
(b) については、見ているのは「過去」ではなく、録画された「映像」、ということである。それはあくまで「今見た」ときに、現実の風景と同じように見ることができるように、工夫し作られた機械的なものである。
「過去」を「今」と同じように見ることはできない。「記憶」や「書物」や「映像」を「今、見たり、思い浮かべる」だけである。それは幻想、というのではなく、過去の「構成的把握」を今しているということである。
(c) の疑問は、不毛というわけではない、くらいしか言えないかも知れない。例えば、過去の出来事(事実)については「記憶」や「書物」や「証言」や「映像」によって今「構成把握」する他ないが、それはある観点での一面性を逃れない。今の世界についても完全には把握できない(事実現象が完全把握できるなら、主客一致である)のだから、過去はもっと曖昧になる。
従って、同様に「宇宙の過去」についても「(今における)過去の痕跡(過去と連続する痕跡)」や「今の宇宙の動きから過去の宇宙を想定して」理解するしかないが、それがどれほど的確なのか、その「的確さ」の話自体が難しそうである。ここには「事実(現実)」を理解するとは何なのか?という問題があり、理念と違い経験的なものなので、その明確さと曖昧さは現実性で判断するしかない。今の宇宙が様々観点での「構成的把握」なら、過去の宇宙は更に曖昧な「構成的把握」である。ただ、宇宙が全くランダムな偶然の動きをするわけではないので、どの程度の確かさで言えるのか、ということである。
不完全性定理の補足 [論理学]
ゲーデルの不完全性定理は大枠で次のように結論づけられると思われる。
数学の基礎づけとして、ヒルベルトにより「形式主義による基礎づけ」が提唱されたが、それはゲーデルの不完全性定理により退けられた。つまり、「形式化」による「数学の無矛盾性の証明」は不完全性定理により矛盾が露呈された。
ゲーデルが証明したのは、一般に語られがちな「数学の敗北(矛盾)」ではなく、「数学の基礎づけとしての形式主義の敗北(矛盾)」である。一つの立場である形式主義に限界があることを証明したということである。
ゲーデルはそのことをよく理解していた、というより彼の論は「形式主義の限界」を目的にしていたようである。「形式主義の限界の指摘」がいつの間にか「数学(の基礎づけ)の矛盾の指摘」のような話になっていった(面がある)、ということである。
間主観について(現象学の基本理念1) [フッサール現象学]
現象学の「間主観」「相互主観」とは何か?
その前に、一般的な意味での相対主義について。
(内容的には、懐疑主義、ニヒリズムも同じ構図である)
相対主義は、人の「絶対的」「普遍真理的」「説教的」な物言いの怪しさ、押しつけがましさから、人にはいろいろな考えがあり、文化も環境も異なるのだから「様々な見方」を許容しようという発想が一つにあると思われる。これは「ごく自然な考え」である。
ただ、一般に相対主義は、あまり詰められたものでないがゆえに、「本来の意図」とは逆の思想になりがちである。
相対主義は、一方で、自説は「正当」と述べているが、他方で、他者の説は「相対的であり正しいとはいえない」(ここで自説が「正しいとはいえない」ことは問わない)というダブルスタンダードな状況にある。
つまり、自説は「正当」、自説の「相対化は問わなく」、他説だけ「相対化する」。
そうすると「相対主義は絶対である」となる。
「相対主義は相対的である」なら、説として成り立たない。そうすると、自分の許可する説だけ「相対的な説」として認め、許可しない説は認めない(その判断の根拠は自分にある)ということになりやすい。
「相対主義」と「絶対主義」が頭の中にあるとすると、「様々な見方を認める」なら、「絶対主義」を認めることになる一方、他方で「相対主義」が「絶対主義」を認めるのはおかしい。
「相対主義」は、「絶対主義」的な考えと同様に、自己視点のみが「超越(客観)視点化」「絶対領域化」しやすく、「同じ根」をもつものである。従って、(「超越視点」どうしがぶつかり)「相対」として成立しないことになる。
従って、相対主義もそれを克服するために複雑化していくこともあるが、基本構図が同じであれば、複雑になっても見かけ上しか変わらないことになる。
日常で「絶対観」「正誤」を突きつめるのは困ることも多く、生活での人生観の相対性、曖昧さは自然なことである。
ただ、そうした日常の「絶対観」「相対観」と、現象学の原理的な構造の問題とは「別のこと」である。アプリオリな本質論は、個人的な趣味嗜好、生活感、心身、社会経済的状態には依存せず、その理解がないと(イデーン「あとがき」にもあるように)現象学は許容されない。自然にそこにあるのではなく、理念的なものなので、「理解が限界」となる。
アプリオリな本質論は、事実(現実)的価値論とは異なる位置にある。価値創造せず、価値構造を見るだけである。ある種の「誤解」は避けがたく、近く見える哲学とも異なることも多く、理解がかなり進まないとその(考え抜かれた)意味が見えてこないのが、「何とも言えない」ところである。
「相対主義」の問題を克服したのが、「間主観」「相互主観」であり、それは無理のない意味での「(超越論的な)相対主義」である。
現象学では、超越視点(客観視点)をもたない。私の視点が全てであり、全ては主観内で閉じ、その外部に出ることは背理である。
(簡単に言えば)外部をエポケー(保留)した主観を、「超越論的主観」という。
超越論的主観の中では、他者も「構成されて」あり、他者も私と同じように「主観」をもつ他者である。
そして、「私」も「他者」と同様にその中で「構成されて」ある。
これを図示すると、次のようになる。
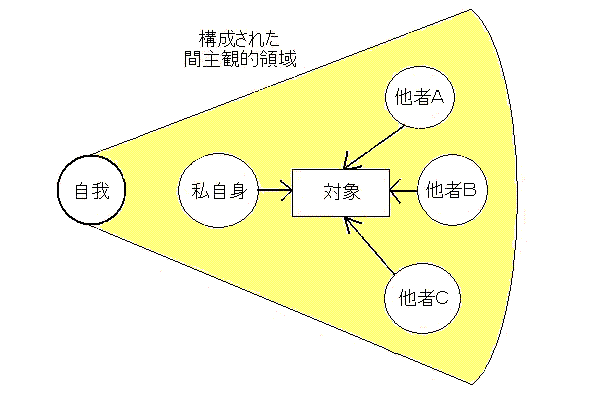
【同一生活世界の経験と認識対象の客観性】
事物や認識対象は、ほとんど自分の生み出したものでもなく、様々な人の中で「作られ」「修正され」「手を加えられ」た客観(相対)的な対象である。対象に対する認識は、他者の経由で客観性が増す。
ある事物(や空間)があるとすると、他者も私も同じ事物(や空間)を経験しているのであり、同一生活世界の中で他者経験を私も経験している。
あらゆる書物にしても、製品、建物、店舗、公共物にしろ、この構図はアプリオリである。
【自己客観化】
「自己主観」も同一生活世界の中で「他者」と同様に「1個の主観」であり、対象化、相対化された主観である。間主観は、そういうことを理解している主観である。
【自我と他我の形相的還元(本質構造の洞察)】
どの主観にも共通構造部分はあり、超越論的構造は誰にとっても普遍的に成り立つ。
能力差、所得格差、社会的格差、性差、身体差、趣味嗜好など、様々な差が人にはあるが、事実的な所有ではなく、自我の本質構造をもつことにおいて平等である。
【理性的な認識】
自己(経験)と他者(経験)は同列にはならない。他者の心理や知覚は自分には経験できず、外面的なものしか与えられない。しかし、他者が、自分と同じような自我の構造をもつと理解するのは難しい話でもない。その意味で、間主観的認識は理性認識であり、その可能性である。
間主観は、自己の頭の中に「共同関係世界」をもつ主観である。自己の「超越化」は間主観性において元々無理がある。
当然、その構造を認識したからうまくいくというのでも、現実がどうにかなるわけでもなく、もしくは、一般社会ではそれはほとんど当たり前のことかもしれない。あくまで原理的なものであり、原理的な部分で混乱、矛盾があればそれが解かれるということでしかない。個々の事実生からは(普遍論なので)影響は受けず、生・生活が破綻していてもそれは関係しない。
フッサールの間主観性の記述は、「他我論」との絡みを含めやや「微妙で難解な」感じになりがちであるが、基本的な発想はこのようなものである(と思われる)。
「超越視点を排した」超越論的な形態において、この「間主観(超越論的相互主観)」が本来の意味での「客観主義」となり、矛盾を克服した意味での「相対主義」となる。(ということが、「ブリタニカ草稿(最終稿)第16節」で簡単に述べられている)
「客観」「客観性」というのは、経験的なものの間主観性と、概念・理念・自我構造の共通性によって支えられている。



